小1の壁とは、子どもが小学校に入学したことをきっかけに、保護者が直面する問題を指します。
「仕事と家庭をどう両立していくか」悩まれる家庭も少なくありません。
延長保育があるため比較的働きやすかった保育園時代に比べて、小学生になると新たな課題が生じ、保護者の負担が増えます。
この記事では、小1の壁の具体的な内容と、それを乗り越えるための対策について詳しく解説します。
- 放課後をどのように過ごさせるかが重要
- 小1は、4時間授業(13時頃下校)か5時間授業(14時頃下校)がほとんど
- 5~7月におこなわれる民間学童クラブの説明会にも参加しておくと◎
小1の壁は、保育園生活からの環境変化で起こる
小1の壁とは、子どもが小学校に入学したことをきっかけに、保護者が直面する問題を指します。
最も大きな問題は、「放課後の過ごし方」です。
特に、共働き(ワーキングペアレンツ)世帯において、子どもの放課後は大きな問題に。
なぜなら、延長保育で18時~19時頃まで預かってくれる保育園とは異なり、小学生の下校時間はぐっと早くなるからです。
4月は給食無しの「午前授業」で小学校が終わることもあります。
多くは4時間授業(13時頃下校)か5時間授業(14時頃下校)となります。
下校時間は、長くても14時半頃。
仕事を終えて帰宅する18時頃までをどのようにして安全に過ごすかを考えなければなりません。
仕事によっては19時を過ぎたり、急な残業が入ったりすることも。
このような環境の変化に伴う仕事と家庭、子育ての両立が難しくなるのが小1の壁です。
小1の壁が起こる原因とは

では、なぜ小1の壁が起きてしまうかを解説します。
時短勤務の対象外となるケースが増加
子どもが小学生になると、時短勤務の対象から外される企業も多くなります。
「もう小学生だから」とフルタイム勤務や残業、出張、休日出勤を求められることが少なくありません。
保護者側も「迷惑をかけた分、会社に貢献したい」と思いつつ、学童クラブの終了時間までに仕事を終えることができず、結果的に退職を選ぶケースも見受けられます。
ただし、会社によってはテレワークや在宅勤務が現在でも定着しており、以前と比べると比較的状況は良くなっているように思えます。
学童クラブの利用に関する課題
学童クラブは、保護者が面倒を見られない時間帯に子どもを預かる施設ですが、利用時間や施設の質に関して課題があります。
一般的に公立の学童(小学校内やその付近にある、行政が運営する学童クラブ)は18時頃に預かりを終了し、延長保育のように柔軟な対応が難しい場合が多いです。
また、地域によっては学童クラブの空きがなく、待機児童問題も発生しますし、学童のスタッフが保育園ほど丁寧に面倒を見てくれないこともあり、子どもが馴染めないケースも考えられます。
仮に小1で学童クラブを利用できたとしても、空き枠の都合上小2.3で利用できなくなることもままあります。
また、スタッフの配置人数は保育園よりも圧倒的に少なくなります。
小1の壁に当たる前に考えること
小1の壁に直面する前に、考えておくべきことをご紹介します。
事前に想定することで急な環境の変化を子どもに与えることなく、金銭的・時間的にも無駄が生じないので、この機会にぜひ考えてみてください。
長期休みの対策
小学生になると夏休み、冬休み、春休みなどの長期休みがあり、その間の子どもの居場所を確保する必要があります。
学童クラブを利用することはできますが、給食が提供されないため、お弁当の用意が必要です。
保育園時代にはなかったこの負担に戸惑う保護者も多いです。
勉強や学校生活のサポート
保育園時代と違い、小学生には家庭学習(宿題)が求められます。
帰宅後の宿題の確認や勉強習慣のサポートが必要で、特に最初のうちは学校に慣れるまでのサポートも欠かせません。
音読や計算カードは保護者が確認する必要があり、これは子どもが起きている時間にやらなければならないのです。
また、毎日の持ち物や連絡プリントの確認、各持ち物への名前付けなど、細かなタスクも保護者に求められます。
学校行事やPTA活動の参加
学校行事やPTA活動が平日に行われることが多く、働く保護者にとってはスケジュール調整が難しいです。
保護者会やPTA会議への参加は、在職中でも免除されないケースが多く、「働いているから参加できない」は理由として認められないこともあります。
また、場合によっては習い事の当番もあり、土日でも自由に過ごせない可能性があります。
子どもの様子の把握
保育園時代は連絡帳や先生からの報告で子どもの日常が把握できましたが、小学校に入るとそういった機会が減り、子どもの学校生活は子ども自身の話を通して知るしかなくなります。
子ども同士の世界が広がり、保護者が把握しきれない部分も増えていきます。
学習にはついていけているのか、友達とは仲良くやれているか、困っていることはないか。
なるべく日々の対話をして、子どもの様子を把握することが必要です。

小1の壁を乗り越えるための5つの対策
小1の壁を乗り越えるためには、次のような対策が必要です。
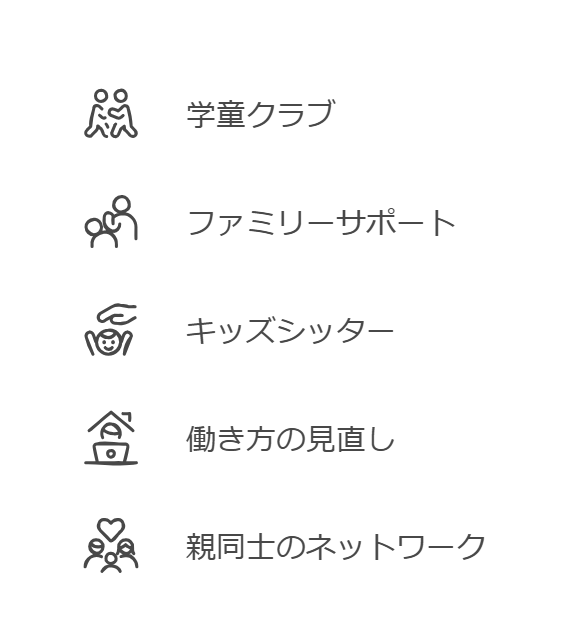
学童クラブの選択肢を広げる
行政が学童クラブの充実を図っており、学童クラブの数や預けられる時間も徐々に増加しています。
公立とはいえ、学童クラブによっては民間企業に運営を委託している場合もあるので、一定の質が担保されているところも多いです。
公立の学童は、基本的には「預かりの場」のため、マンガを読んだり遊んだりして過ごします。
公立とは別で、民間学童クラブも都心を中心に増えています。
民間学童クラブは、公立と比べると単価は高いものの、英語や運動の指導、延長保育、送迎など多様なサービスを提供しているところが多いです。
各施設の特徴やサービスを事前に調べ、見学や会員登録をしておくと良いでしょう。
なお、民間学童クラブの多くは、5~7月頃に次年度の募集のための説明会をおこないます。
「うちは公立の学童クラブを利用するから」と決めつけず、どのような状況になっても対応できるよう、説明会だけでも参加しておくことをおすすめします。
ファミリーサポートを活用する
各自治体が運営するファミリーサポートは、30分~1時間単位で安価に子どもの送迎や預かりを依頼できるサービスです。
月曜日~土曜日の午前9時~午後5時…1時間 900円
月曜日~土曜日の午前7時~9時、午後5時~9時…1時間 1,100円
日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)…1時間 1,100円
地域のサポーターが活動しており、必要な時に柔軟に対応してもらえるため、利用してみると良いでしょう。
キッズシッターを利用する
ファミリーサポートよりも料金は高くなりますが、専門のキッズシッターに子どもを預けることで、英語や学習支援を含むプロのサービスが受けられます。
安心して預けたい保護者にとっては、有力な選択肢となるでしょう。
働き方の見直しと調整をする
職場に事情を説明し、時短勤務やテレワークの利用を相談してみましょう。
今の職場での調整が難しければ、退職や転職も視野に入れ、子育てと両立しやすい働き方を模索することが重要です。
親同士のネットワークを活用する
子どもの持ち物確認や友達関係について、情報交換ができる親同士のネットワークを築くことも、小1の壁を乗り越えるために有効です。
登校班や幼稚園・保育園時代のつながりを大切にし、頼れる仲間を見つけましょう。
MAMATALK(ママトーク)というママ友を見つけるアプリもあります。身近に相談できる人がいない場合はこのようなサービスを利用してもいいでしょう。
さいごに
- 放課後をどのように過ごさせるかが重要
- 小1は、4時間授業(13時頃下校)か5時間授業(14時頃下校)がほとんど
- 5~7月におこなわれる民間学童クラブの説明会にも参加しておくと◎
小1の壁は、多くの保護者が直面する大きな課題ですが、準備をしっかり行い、周囲のサポートを活用することで乗り越えることができます。
子どもの成長を信じ、自立心を育てながら、無理をせずに柔軟に対処していきましょう。






コメント